こんにちは、管理人のmilkyです。当ブログではアフィリエイト広告を利用しております。
気づけばついスマホを開いてしまう…。SNSをだらだら眺めたり、ゲームを無限にプレイしてしまったり。私もそんな スマホ依存 に悩んでいました。
でも、あるきっかけから「本を読む習慣」を持つことで、自然とスマホを触る時間が減り、気持ちまで軽くなったんです。
今回はシリーズ「スマホ依存から抜け出す読書術」の第1回として、なぜ“読書”がスマホ依存から抜け出すのに効果的なのか、その理由をお話しします。
📌 なぜ本を読むとスマホ依存から抜け出せるのか?
-
「ながら時間」を本に置き換えられる
病院や電車の待ち時間など、なんとなくスマホを触っていた時間を本に充てられる。これだけで「ダラダラした時間」が「学びや発見の時間」に変わります。 -
集中できるから心が満たされる
スマホは次々と情報が流れてきますが、本は1ページずつ自分のペースで読み進めます。集中して読み終えると「達成感」があり、自己肯定感も上がります。 -
視野が広がる
自己啓発本、小説、ビジネス書…。本を通して新しい考え方やストーリーに触れることで、スマホにはない「深い学び」や「新しい会話のネタ」が手に入ります。
📖 このシリーズについて
このシリーズでは、私が実際にスマホ依存から抜け出すきっかけになった本を1冊ずつ紹介していこうと思います。
-
『行動経済学BEST100』
-
『夢をかなえるゾウ』
-
『金持ち父さん貧乏父さん』
読んだ感想や、どんなふうにスマホとの向き合い方が変わったのかを体験談ベースでお届けします。






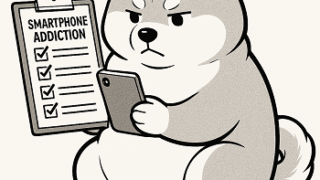
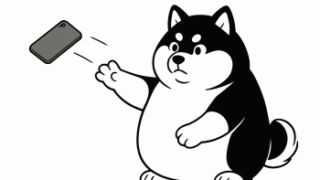

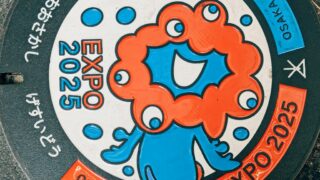

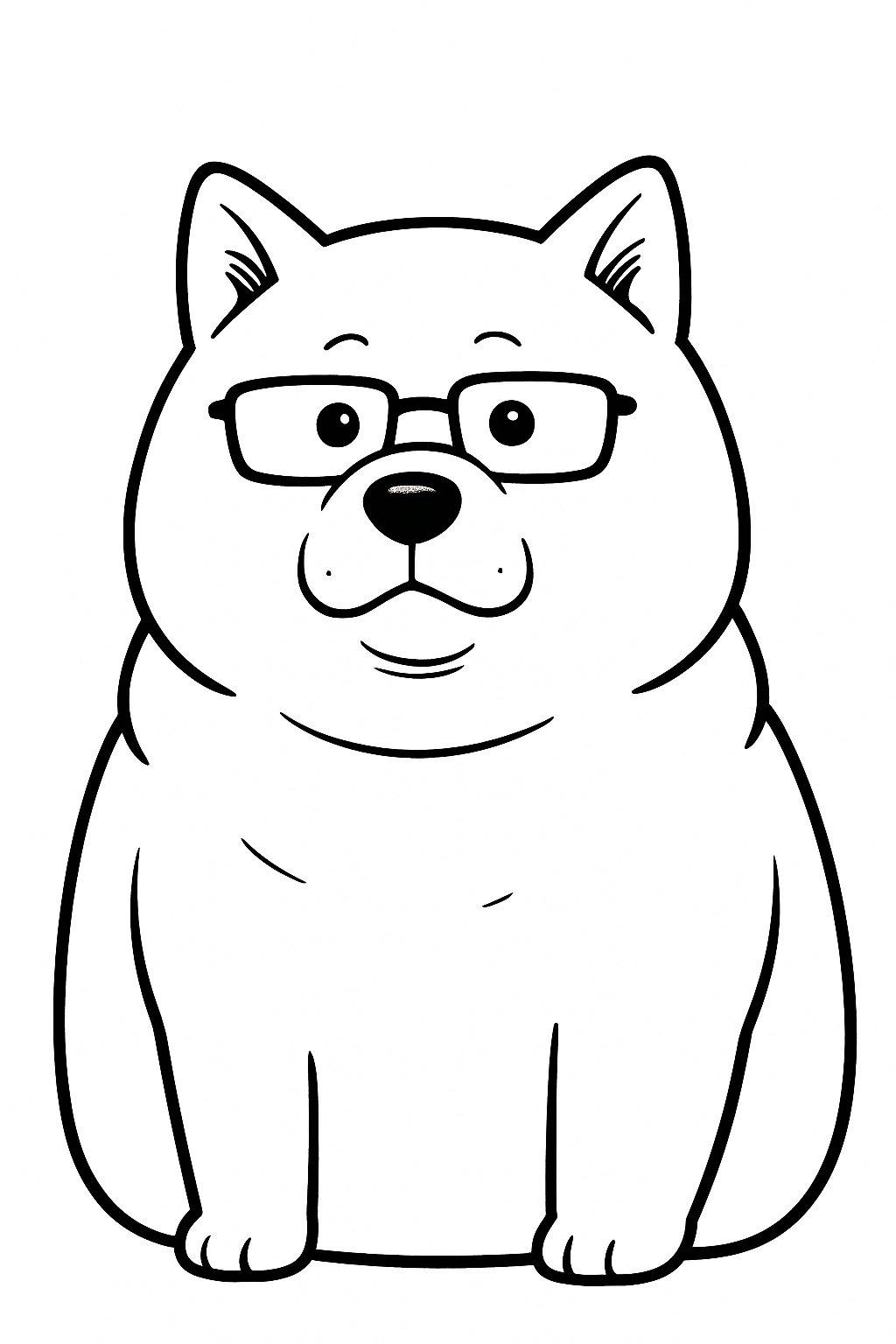

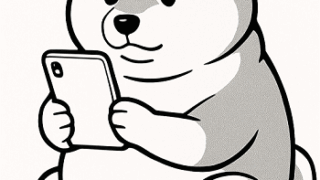
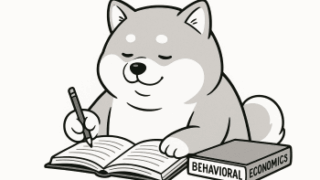

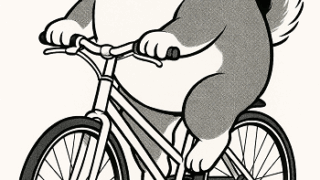







コメント