こんにちは、管理人のmilkyです。当ブログではアフィリエイト広告を利用しております。
今回は、誰でも簡単にスマホ依存症かどうかチェックできる方法をご紹介していこうと思います。
気になるツールや方法があったら、ぜひやってみて下さいね^^
1.代表的なセルフチェックリスト(4つ以上該当で依存の疑い)
-
-
家や職場で常にスマホが手に取れる場所にある
-
疑問が浮かぶとすぐスマホで検索する
-
少しでも時間が空くとスマホを触る
-
家にスマホを忘れると強い不安を感じる
-
目的もなく無意識にメールやSNSをチェックしてしまう
-
就寝直前までスマホを操作している
-
スマホのスクリーンタイムが1日2時間を超える
-
着信音やバイブの空耳が聞こえることがある
-
調べ物はほぼスマホで済ませている
-
飲食店選びなどでネットの評判を重視する
-
-
判定基準
-
4つ以上当てはまる場合は「スマホ依存の疑い」
-
3つ以下でも「スマホに頼りきった生活」と感じる場合は予備軍
-
6個以上で「赤信号」とするチェックリストもある
-
セルフチェックの結果はいかがだったでしょうか?
スマホ依存または予備軍の方はさらに下記の項目もチェックしてみてくださいね!
自分のスマホ依存度を正確に把握する方法は、以下の手順やツールを活用することで実現できます。
2. 科学的な診断スケールを利用する
「スマートフォン依存スケール(SAS)」や「インターネット依存度テスト(IAT)」など、信頼性の高い診断テストを使うことで、依存度を客観的かつ数値で評価できます。これらは15~25問程度の質問に答える形式で、依存度を6段階や4段階で判定します。
例えばSASでは「スマホでの文字打ちに費やす時間」「使用目的」「生活への影響」などを多角的に評価します。
スマートフォン依存スケール(SAS:Smartphone Addiction Scale)は、韓国のKwonらによって開発された、スマートフォン依存の重症度やスクリーニングを目的とした評価ツールです。
短縮版(SAS-SV)では思春期・青年期向けに10項目にまとめた短縮版(SAS-SV)があり、より簡便にチェックできます。
SAS-SVの日本語版(SAS-SV-J)も作成されており、日本国内の臨床や研究で広く利用されています。
こちらのSAS-SVは医療機関のウェブサイトなどで公開されており、誰でもセルフチェックが可能です。スマホ依存かどうか性格に把握したい方は、ぜひチェックして診断してみてください。
3. オンライン診断ツール・アプリの活用
スマホ依存のセルフチェックができる無料のオンライン診断やアプリが多数あり、24時間いつでも簡単に診断できます。診断結果はグラフや数値で表示されるため、依存度を視覚的に把握しやすいのが特徴です。
代表的なアプリには、利用時間の自動記録やアプリ別の利用傾向分析、改善アドバイス機能などが搭載されています。
スマホ依存の診断や対策に役立つアプリには、使用時間の可視化・依存度診断・強制制限など多様な機能を持つものが揃っています。主なおすすめアプリと特徴は以下の通りです。
| アプリ名 | 主な機能・特徴 | 対応OS | 料金 |
|---|---|---|---|
| StayFree | アプリごとの使用時間やチェック履歴の可視化、アプリ・Webサイトのブロック機能。依存度をグラフで確認。 | iOS/Android | 無料 |
| Forest | スマホを触らずに集中すると仮想の木が育つ。楽しみながら依存対策。 | iOS/Android | 有料(250円など) |
| Detox | 設定時間中はスマホを完全ロック。途中解除不可の本気仕様。必要なアプリのみ例外設定可。 | Android | 無料/有料 |
| Flipd | タイマーでスマホをロック、集中時間の記録や音楽再生も可。学習・仕事向き。 | iOS/Android | 無料/有料 |
| UBhind | アプリ別の使用時間を詳細にグラフ化、目標超過時は自動ロック。 | Android | 無料/有料 |
| AppBlock | アプリ単位でブロック、柔軟なスケジューリング。 | iOS/Android | 無料/有料 |
| YourHour | 依存度診断機能付き、使用習慣の自動計測。 | Android | 無料/有料 |
| スマホスピタル | スマホ依存症度を診断できる日本語アプリ。 | iOS/Android | 無料 |
診断系機能のポイント
-
StayFreeやYourHourは、日ごとの使用時間やアプリ別利用傾向を自動で記録し、「依存度スコア」やグラフで可視化します。
-
スマホスピタルなど一部アプリは、質問形式で依存度診断が可能です。
-
DetoxやAppBlockは、診断だけでなく物理的な制限機能も強力です。
選び方のコツ
-
まずはStayFreeやYourHourなど、無料で依存度診断・可視化ができるアプリから始めるのがおすすめです。
-
強制的に制限したい場合はDetoxやFlipd、Forestなどを活用すると効果的です。
注意点
-
アプリによる診断はあくまで目安です。深刻な依存傾向が見られる場合は、専門家への相談も検討してください。
デジタルウェルビーイングに関心がある場合、これらのアプリを活用して日々のスマホ利用を客観的に把握し、適切なセルフコントロールを目指しましょう。
4.専門機関での診断
スマホ依存について専門機関で診断を受けるには、以下の手順やポイントを参考にしてください。
1. 専門外来・医療機関を探す
-
スマホ依存やネット依存、ゲーム障害を専門に扱う「ネット依存外来」「依存症専門外来」が全国に設置されています。
-
公的なリスト(例:久里浜医療センターの治療施設リスト、全国依存症専門相談窓口・医療機関検索サイト)を利用すると、地域ごとの専門医療機関を探せます。
2. 受診の流れ
-
初診時は、本人や家族に対して生活習慣・スマホやネットの使用状況・日常生活への影響・対人関係の問題などを詳しく問診します。
-
必要に応じて、スマートフォン依存スケール(SAS)やインターネット依存度テスト(IAT)などの診断尺度を用いて、依存度を科学的に評価します。
-
心身の健康状態を確認するため、血液検査や身体測定、精神状態の評価なども行われる場合があります。
3. 診断のポイント
-
スマホやネットの使用がコントロールできない
-
日常生活や学業・仕事に明確な問題が生じている
-
問題があってもやめられない
-
これらの状態が12カ月以上続いている場合、医学的な診断(ICD-11等)に基づき「依存症」とされることがあります。
4. 受診の際の注意
-
依存症専門医療機関は限られているため、事前に電話やウェブで予約が必要な場合が多いです。
-
学生や未成年の場合は、保護者の同意や同伴が求められることがあります。
5. 相談・情報収集
-
まずはセルフチェックやオンライン診断ツールで傾向を把握し、深刻な場合や生活に支障が出ている場合は、専門機関への受診を検討しましょう。
スマホ依存の診断は、専門外来での問診や科学的な診断尺度の活用、必要に応じた健康チェックを通じて行われます。まずは専門医療機関を探し、予約・受診することが第一歩です。
まとめ
今回は、スマホ依存かチェックできるツールと方法をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
スマホばかり触っていて時間を無駄にしている気がしている・・・
目にもよくないし見るのをやめたくてもやめられない・・・
そんな方はぜひ一度、今回の方法をチェックしてみてくださいね!
それでは今回はここまでとさせていただきます。さようなら!
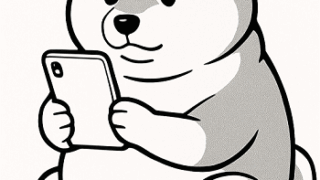






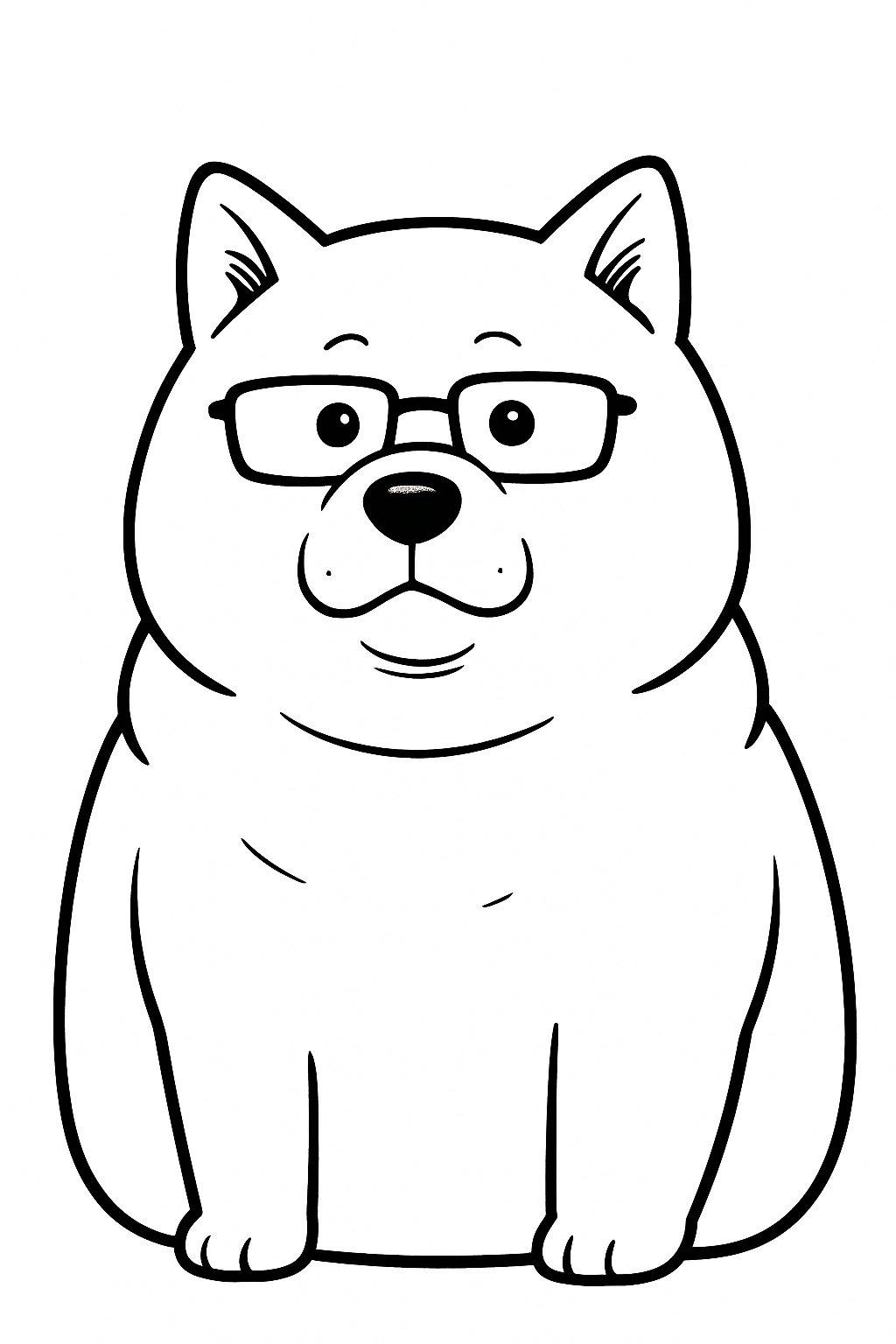
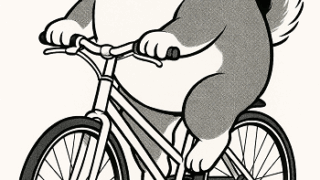
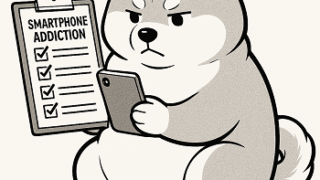


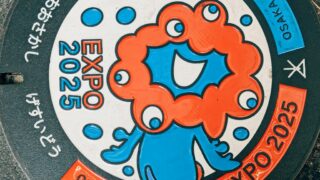




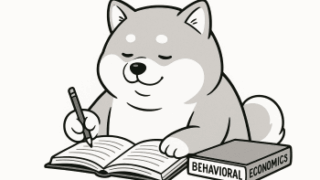



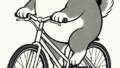

コメント